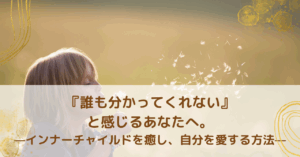私の幼少期は、決して平穏なものではありませんでした。
複雑な家庭環境の中、
子供ながらに常に周囲の顔色を伺い、
いつも孤独を抱えて過ごしていました。
そんな私の「止まり木」になってくれたのは、
近所に住むおばあちゃんでした。
「ウェルビーイング」という言葉を聞くと、
多くの人は、よく運動し、健康的な食事を摂り、
心身ともに充実したアクティブな生活を
イメージするかもしれません。
けれど、私にとっては
「静かで、誰かに自分を委ね、
心を通わせ、体温を感じられる時間」
の中にあります。
そう、思うのは幼いころの私の記憶です。
幼少期、私の家のそばには原っぱがあり、
そこにはドラえもんに出てくるような
コンクリート製の大きくて長い土管が三つ、
重ねて置いてありました。
そこは近所のおばあちゃんの定位置。
おばあちゃんは、
いつもその一番下にある土管に腰をかけて
子供たちが集まって来るのを待っていました。
冷たくて硬いはずのその土管は、
おばあちゃんが座っているだけで、
不思議と陽だまりのような場所だったのです。
私は小学校から帰ると、
一目散に、原っぱにいるおばあちゃんのところへ走っていきました。
いつもおばあちゃんの周りには
幼稚園から小学校6年生までの
7、8人の女の子が集まっていました。
その周りでは数人の男の子たちが、
ボールを蹴ったり、かけっこをしたり。
おばあちゃんは
みんなに優しい眼差しを向け、
「この子だけ特別」という
差別を全くしませんでした。
男の子の中に、ひとり、
近所で嫌われている有名な子がいました。
いつも大声を出していて、
洋服がしわくちゃ、鼻水で顔が汚れている。
近所の大人たちは、そんな男の子に眉をひそめ、
「あの子に近づいたらダメ」と、
接近禁止令を子どもたちに出していました。
ですが、おばあちゃんは差別をしません。
彼に対しても、みんなと同じように
優しい眼差しを向けていたのです。
何か特別である必要はなく、
誰に対しても平等。
ただ、そこに居て、
ただ、ありのままを
受け入れてもらえる。
おばあちゃんがいる空間は
絶対的な安心、安全基地だったのです。
子供たちが集まると、
絵本や紙芝居の読み聞かせが始まります。
日本昔話からグリム童話まで、
おばあちゃんが語る世界は星のようにいっぱい。
私が大好きだったのは、
「長靴をはいた猫」「シンデレラ姫」など、
お姫様が出てくる物語でした。
美しいお城、きらびやかな舞踏会、綺麗な裾の長いドレス。
そして、お姫様を優しく見守る味方たち。
ひときわ私の心を魅了したのは、
どんな困難に見舞われても、
最後には必ず素敵な王子様が現れて
助けに来てくれるハッピーエンドの世界です。
おばあちゃんの穏やかな声に導かれ、
私はひととき現実を忘れ、
まばゆい夢の世界へと連れていってもらいました。

当時の私は、
物語とは正反対の「灰色」の中にありました。
母は「統合失調症」という病気を持っていました。
常に人の目を怖れ
「近所の人が私をバカだと言っている」と、怒り、
家中の雨戸を閉め切っていました。
チャイムが鳴れば、
一緒に万年床の布団に隠され
「しっ、声を出したらダメ」と、
立ち去るまでジッとしている。
テレビに出ている数字が怖いといって
耳を塞ぎながら「ワ~、ワ~」と言う。
綺麗な色を見るのが怖い。なので、私は大人用のサイズが合わない灰色の服をいつも着せられていたんです。
幼心にも「ヘンなお母さんだな」と、
分かっていても、どうすることもできません。
ただ、母の言う通りにして過ごすしかない。
だけど、本当はお姫様みたいに
ピンク色の可愛い洋服を着たかったし、
きっと甘えたかったのです。
すべて本当の気持ちを奥底に沈め、
私はいつしか感情を押し殺し、
「そんなお母さんでも守らなきゃ」と、
歯をくいしばって頑張っていたのです。
だからおばあちゃんの話す物語は
私を現実から解き放してくれる
唯一の救いでした。
星のようにまばゆい「夢の世界」へと
連れていってくれる、
物語の中に入りこみ、
綺麗なドレスを着て、
王子様と踊る。
きっとその時、
私は目をキラキラと輝かせていたに違いありません。
私はこのおばあちゃんのいる
土管のある原っぱに6年生まで通っていました。
今振り返れば、
私が求めていたのは物語そのものだけではありません。
おばあちゃんのまんまるい背中、
静かな声のトーン、
ゆっくりと紙をめくる皺の深い手。
私が欲しかったものが、
全部そこにあったのです。
そこには、学校の先生や他の大人が口にする
「勉強しなさい」
「明るい子でいなさい」
「ちゃんとしなさい」
といった、私を縛り付ける言葉は一切ありませんでした。
おばあちゃんが作ってくれる時間だけは、
身を任せ、呼吸ができて、心を預けられる。
この「委ねられた時間」こそが、
傷ついた私の心を静かに癒やしていたのだと、
大人になってから気づきました。
ウェルビーイングの重要な要素の一つに
「他者との良好な関係」があります。
けれど、単に友達が多いことや、
社交的であることではないと思うのです。
孤独で逃げ場がなかった私にとって、
おばあちゃんがくれた
「現実を忘れて、誰かに心を委ねられる時間」は、
生きるための切実な安全基地でした。
まだ子供で、どう頑張ればいいのか分からず、
それでも「ちゃんと」しなきゃと震えていた私にとって、
人の優しさに身を委ね、
つながりを感じることは、
何よりの救いだったのです。
人は、人との関わりの中で傷つくこともあります。
けれど、その傷を癒やし、
再び前を向く勇気をくれるのもまた、
人との繋がりなのだと、
今は胸の奥で噛みしめることができます。
大人になると、つい
「自立しなければ」
「強くあらねば」
と肩を張って生きてしまいがちです。
だけど、子供の頃、
お母さんに自分の本当の気持ちを話せなかった、
そもそも言葉をどう表現したらいいのか、
分からなかった。
そのときの心は、
そのまま置き去りとなり、
「人に頼ってはいけない」、
「どうせ愛されない」、
「弱さを見せちゃいけない」、
と心が助けを求めているかもしれません。

この令和の時代、
SNSでなにかひとつでも言葉を間違えると
批判を浴びるような、
常に緊張を強いられる世界。
これでは自分を委ねるなんて、
怖くて出来ない時代になっている気がします。
SNSのキラキラした虚勢を
張らなければならない世界で、
誰かに弱さを見せ、
自分を委ねることは
とても勇気がいるでしょう。
けれど、ありのままではいられないことは
何よりも苦しいことです。
私の学ぶハコミセラピーでは
「人は安全と安心の場所がないと絶対に変われない」
といいます。
私自身も、
心の底から安心できる場所で
自分を委ねられたからこそ、
過去の怒りや、悲しみ、寂しさを癒し、
変わることができました。
今度は私がセラピストとして、
「人が委ねられる場所を創っていきたい」。
それが今の私の、
ウェルビーイングの大切な一部となっています。

今、あの土管の原っぱは住宅地になり、
跡形もありません。
でも不思議なことに、
ふと、おばあちゃんの存在を近くで感じるのです。
おばあちゃんが今の私を見たら、
きっと何も言わず、
「まあ、ちゃんと生きてるね」と、
あのまんまるい背中で笑ってるような気がするのです。
そう思える今の私は、
たぶん――けっこう、幸せです。
最後まで読んでくださり、
ありがとうございました。
あの原っぱのような
「安心できる場所」を、
今はセラピストとして形にしています。
もし、今のあなたに
「心を委ねる場所」が必要でしたら、
プロフィール欄から私の活動をご覧いただければ幸いです。